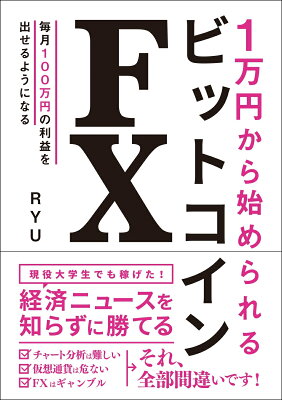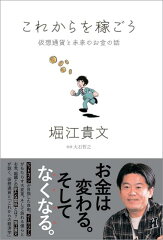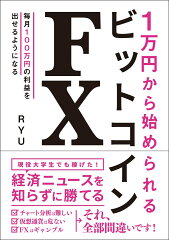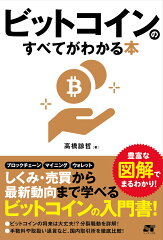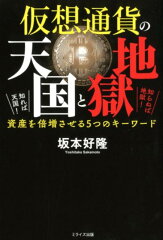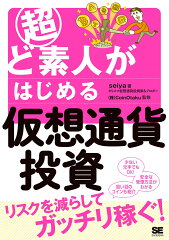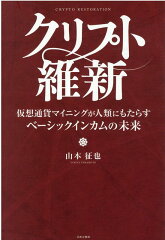- 1. なぜ日本人はビットコイン・仮想通貨を買わないのか
- 2. 日本人のマネーリテラシーとビットコイン・仮想通貨
- 3. 日本はお金持ちが多い?
- 4. 日本人がビットコインなどの仮想通貨をまだ持っていない人が多い理由=貯金好き
- 5. ビットコインや仮想通貨を持たない理由=NISAもiDeCoも財形もしていないから
- 6. 日本人が資産を保有してもビットコインバブルに乗れなかった理由
- 7. 過保護すぎる日本の法律がビットコインを遠ざける
- 8. 参考:ICOとIEOとは
- 9. なぜ日本人は『今』ビットコインを買わないのか
- 10. 『ビットコインが買われない理由』はビットコイン・仮想通貨が浸透しにくいから
- 11. そもそもなぜここまで日本はマネーリテラシーが低いのか
- 12. 日本人はビットコインや仮想通貨・暗号資産を買うべきなのか
- 13. 仮想通貨の参考文献・参考書
- 14. 関連記事
なぜ日本人はビットコイン・仮想通貨を買わないのか
ビットコインと日本人の思考
ビットコインや仮想通貨がどれだけ投資や資産運用のチャンスだと分かっていても、実際に保有している日本人の投資家は多くありません。
なぜビットコインや仮想通貨は世界的に見れば儲かる投資なのにも関わらず先進国の日本は浸透し・保有率が上がらないのでしょうか。
日本人のマネーリテラシーとビットコイン・仮想通貨
日本人の思考はリスクを取らずにゲインを逃す、というパターンに長年ハマったままです。
理由は何より日本のマネーリテラシーの低さだと言われています。
日本はアジア諸国で14カ国内でマネーリテラシーが最下位です。
そしてマネーリテラシーの指数要素と言われる3カテゴリー(金銭管理・財務管理・投資)の中で13位と10ポイント以上差をつけられている状態なのです。
日本はお金持ちが多い?
日本は1998年から他国比較をすると、家計の成長度が極めて低く、運用資本比率で1,4倍しか伸びていません。
つまり、資産運用や投資ができるだけの十分な知識やスキルを持つことをしてきていなかったことが原因だと言えます。
ちなみに、日本人の家計で金融資産構成費のうち、たった15%しか株式投資などの資産運用に資産が使われていなかったことがわかっています。(FRB,BOE,日本銀行による金融庁作成データより)
アメリカはその倍以上の34.4%株式投資などに充てているデータもあります。
そのため複雑な分析をせずともビットコインがアメリカでインフラに根付くスピードが早かったのも、マネーリテラシーが根底にあったと言えます。
日本人がビットコインなどの仮想通貨をまだ持っていない人が多い理由=貯金好き
日本人の中でビットコインという言葉や仮想通貨というワードを聞いたことがない、という方はおそらくかなりの少数派だと言えます。
ビットコインや仮想通貨・暗号資産について、知っているのにも関わらず投資・運用などをしない・保有していない理由は『貯金が好き・現金が好き』だからです。
アメリカでは14%ほどを預貯金とし、イギリスでは24%ほどの構成費である現金が日本は52%と圧倒的な構成比なのです。
つまり、日本人はそもそも『増やす』より貯める・リスクを怖がる性格が強いと言えるのです。
そのため、同じ資産額を持っている海外の友人とは必然的に、10年後・20年後の資産額に大きな乖離が生じることになります。
ちなみに、アメリカと日本を20年後運用結果を比較すると約2倍の差が開くことになります。
ビットコインや仮想通貨・暗号資産を第一次仮想通貨バブルの時に保有している日本人投資家が多ければ、今の日本経済はまた違う方向に首を向けていたとも考えられるのです。
ビットコインや仮想通貨を持たない理由=NISAもiDeCoも財形もしていないから
NISAやiDeCoなど税制優遇措置があり、比較的リスクの少ないファイナンスカテゴリーであっても、財形は約50人に1人しかやっておらず、iDeCoに関しては約100人に1人しかしていないのです。
つまり、どれだけ情報を知り得る環境にいても、マネーリテラシーを抜本的に改革しない限り日本は先進国であり続けることすら危ぶまれるのです。
 日本人でビットコイン・仮想通貨を保有した投資家と運用リターンの仕組み
日本人でビットコイン・仮想通貨を保有した投資家と運用リターンの仕組み
日本人のマネーリテラシーの低さに愕然としながらも、日本で仮想通貨・暗号資産によって資産を倍増させた投資家も存在します。
しかし、残念ながら第一次ビットコインバブルが起こった時に、運用リターンが大きく確保できた投資家は、資産家と言われるようなクジラのような存在でした。
参考:ビットコイン・仮想通貨でのクジラとは?
ビットコインであれば1,000BTC(約5.5億円)以上=クジラと位置付けられ、大口投資家・資本家を意味します。
1,000BTC(約5.5億円)以上保有するアドレスの数は約2334件あり、この2334件がビットコイン・クジラの生息数であり、その2334匹のうち上位20%がビットコインの流通量全体の80%以上を保有していると言われています。
2017年のビットコインバブル時に確定申告の総括が国税庁から公表され、「雑所得の収入が1億円超あったとした納税者のうち、仮想通貨の売買で収入を得ていた人が少なくとも331人に上る」と発表され、たった331人しかこの大きな経済バブルの波になれなかったことに機会損失を気付かされることになります。
▷▷▷【初心者〜経験者まで必読】これを読めばわかる『ビットコイン』関連の本
日本人が資産を保有してもビットコインバブルに乗れなかった理由
マーケティングの基礎理論として知られるイノベーター理論を日本人に当てはめてみる
- 「イノベーター(Innovators:革新者)」
- 「アーリーアダプター(Early Adopters:初期採用者)」
- 「アーリーマジョリティ(Early Majority:前期追随者)」
- 「レイトマジョリティ(Late Majority:後期追随者)」
- 「ラガード(Laggards:遅滞者)」
の5つのタイプに区分されると言われています。
参考:イノベーター理論とは?
イノベーター理論とは、消費者を5つの層に分類することにより、新しい商品やサービスがどのように市場に普及していくのかを分析した理論です。
新しい金融商品などを含む、新製品、新サービスが市場に登場すると、冒険的で最先端を重視するイノベーターがまず利用・保有・購入をしていきます。
そして次に情報感度の高いアーリーアダプターが追従する仕組みになっていきます。
ここでようやく、新聞やメディアなどでアーリーマジョリティが動き始めます。
ここからは段階的に逓増し逓減が始まる波が形成されます。
そもそもアーリーアダプターとアーリーマジョリティとの間にはキャズムという格差・溝があると言われており、イノベーターと比較するとアーリーマジョリティですら機会損失を受けることになります。
みなさんは日本人、あるいは自分がどこに位置づくかお分かりでしょうか?
日本人の多くは特に金融商品やデリバティブ商品に疎く、早くてレイトマジョリティ、平均がラガードの位置付けになっていきます。
特にビットコインや仮想通貨・暗号資産に関しては、日本特有の問題もあり浸透が未だに遅れていると言えます。
過保護すぎる日本の法律がビットコインを遠ざける
暗号資産を資産とするデリバティブ取引を金商法の規制対象に追加し、店頭デリバティブ取引を業として行う場合には、第一種金融商品取引業登録が必要です。
外国為替証拠金取引(FX取引)と同様に、金商法上の規制(販売・勧誘規制等)を整備 証拠金の上限倍率(レバレッジ倍率)を、 暗号資産の種類によらず2倍としています。
ICO・IEOは資金決済法における暗号資産規制のもとで実施されるべきというモラルハザードを政府が提起しているため、日本ではICO・IEOによる資金調達は海外よりも非常にハードルが高いことになります。
ICO・IEOは新規事業者の資金調達に用いられますが、投資家からすれば破格でスタートアップ時の価値で『期待』『アクティブ・リスク』を選ぶことができるため、数%でも資産ポートフォリオに入れられる選択肢は欲しいと言えます。
ちなみに日本では2021年7月に仮想通貨取引所のCoincheckが、Coincheck IEOをスタートし、パレットトークン(Palette Token /PLT)のIEOを実施しました。
参考:ICOとIEOとは
暗号資産のICOとは『Initial Coin Offering』の略で同義語では『クラウドセール』『トークンセール』『トークンオークション』とも呼ばれることがありますがどの意味も、新規暗号資産(仮想通貨)公開のことです。
IEO(Initial Exchange Offering)は、仮想通貨取引所のサポートを受けてトークンを販売することを言います。
仮想通貨・暗号資産のトークンを開発する企業やチームはなぜICOやIEOを行うかというと、新規発行トークンを投資家に提供する代わりに返済義務の生じない融資を受けることができます。
つまりは、利息も利子も手数料もかからず使途も自由なのです。
これは金融機関などの融資ではあり得ないことで、『いくら何に使うか』そして『いつ・何にいくら使ったか』の追求もないため使途不明金などと言われることがないのです。
この利用用途に拘束がない資金は、あらゆるトラブルなどでも有効的に使えるため新規の仮想通貨・暗号資産を開発する企業やチームはトライしようとするのです。
なぜ日本人は『今』ビットコインを買わないのか
ビットコイン・仮想通貨投資は税金が高すぎる
仮想通貨取引による所得は、給与所得などの各種の所得金額の合計額に課税される総合課税制です。
所得額が大きくなるほど税率が上がる累進課税で、最高で45%(住民税・復興特別所得税を含めると約55%)の所得税が課されます。
株式投資やFXは、租税特別措置法によって特例的に税率が約20%に軽減される上に、損失を翌年以後3年間にわたって繰り越しできますが仮想通貨・暗号資産での損失は翌年以降への繰越は原則できません。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円を超え 4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
(参考データ引用元:国税庁ホームページ )
『ビットコインが買われない理由』はビットコイン・仮想通貨が浸透しにくいから
ビットコインなどの仮想通貨を決済に使用した場合も「仮想通貨を使用することで生じた利益」にみなされます。
仮想通貨で買い物をしたり、他の仮想通貨と交換しても課税対象です。
つまり、ビットコインなどの仮想通貨で現金やデジタルマネーと同じように買い物をするだけでも課税対象になってしまうのです。
では、この税制度で一切資産形成ができないのか、と言われるとそうではありません。
例えば、ビットコインをETF(上場投資信託)化した、『ビットコインETFや仮想通貨ETF』と呼ばれる商品で発生した所得・収益は申告分離課税に該当します。
一方ビットコインを現物で保有すると総合課税扱いになります。
さらに言えば不動産などへの投資を行っている場合や、給料や報酬として投資以外に収入がある場合は総合課税扱いの所得と分ける方が節税・税金対策になると言えます。
細かくここでは取り上げませんが、現在の控除額で計算すると所得が330万円を超えている場合は、ビットコインETFの方が税金が低くなります。
このような特性を活かすと日本でも、ビットコインや仮想通貨・暗号資産で資産運用をしたり、資産形成を成功させるチャンスはあると言えます。
参考:申告分離課税と総合課税の違い
ETFや株式投資などの売買で所得が生じた場合など、他の所得とは分離して税額を計算し、確定申告によって納税する課税方式です。
総合課税の対象となる他の所得などと分離されるため、該当する所得金額にのみ一律20.315%(所得税15%+住民税5%+復興特別税0.315%)が課されます。
土地または建物等の譲渡による所得のような申告分離課税の対象となる他の所得とも分離して課税が行われます。
一方、総合課税は対象となるすべての所得を加算してその合計金額に対し課税する方法のことです。
個人所得のうちETFや株式投資など山林所得、土地建物等の譲渡所得などを除く、各種の所得金額を合計し税額を計算して確定申告により税金を納付する制度です。
そもそもなぜここまで日本はマネーリテラシーが低いのか
お金の教育はできない・受けられない環境に日本はある
『なぜここまで日本はマネーリテラシーが低いのか』という疑問を感じる方もいると思いますが、これは一般的には郵便貯金の定期預金の金利が7.5%ほどあったため、郵便局に預金・貯金するだけで、自己資産は10年で2倍近くになる時代があったからだとされています。
▷▷▷まだ定期預金はやるべきなのか?活用方法・メリットはある?
定年まで働いて、貯金をし税金を納めていれば金利と年金で一生を終わらすことができた時代の名残だとも言われています。
確かに、金融機関への預け入れであれば元本割れのリスクも破綻時の補償もあるため、リスクはゼロに等しいと言えます。
しかし、今は金利はゼロに近く、終身雇用も薄れ、極度のインフレに資産は増えるどころか減る状態になっていることを若者に教える人や環境がないということに原因があるとされています。
さらに若い学生などに『お金』について教える人・教えることのできる人がいないとも言えるのです。
なぜなら、そもそも日本人のほとんどが資産構成を預貯金で占めており、マネーリテラシーに長けている人が教職に就くことにメリットがないためです。
仮に、マネーリテラシーを親や家族が教えるならば、親が資産運用や資産形成の実績・知識・経験を持ち合わせていないため現実的に今の日本では不可能に近いと言えます。
もちろん、大学では経済学・経営学を学ぶことができますが、ある程度の大学で在籍しないと本当にマネーリテラシーのある講師の話を聞くことはできません。
▷▷▷『まだ続ける?』『まだ信じる?』間違った金融リテラシー
日本人はビットコインや仮想通貨・暗号資産を買うべきなのか
金融・経済知識を自身の生活環境や経済環境で活用できるか検証するマネーリテラシーは、学校では教えてくれません。
その中で日本人はビットコインや仮想通貨・暗号資産を保有し購入するべきなのか。をまとめておきます。
ビットコインは開発時から希少性を発生させインフレを抑制させるため、発行上限枚数が2,100万BTCという発行総量が決まっています。
2019年に約80%、既に1,800万BTC分は世に出ており発行が完了していますが、半永久的にアクセスできない状態になっている約400万~600万BTCのビットコインがあるとされ、実質1200万BTCほどしか流通していないことになります。
世界総人口70億人に対して一人当たりのビットコイン数量は0.0027 BTCしかないと見積もられています。
ビットコインは通貨インフレを抑制させるため4年に1度の半減期も設定されており、自然と発行枚数がリバランスされていく仕組みになっています。
つまり、日本の法定通貨の発行枚数は日本銀行が決めており、中央集権的な管理体制がある上で経済が成立しています。
しかし、この中央集権的な管理体制で満足いく生活がみなさんができていないならば、ビットコインなどの希少性が発生する仮想通貨・暗号資産を保有することがリスク対策になりうると言えます。
ブロックチェーン実践入門 ビットコインからイーサリアム、DApp開発まで [ Bikramaditya Singhal ]
関連記事 |
| 【初心者向け】仮想通貨ETFとは?儲かるのか? |
| ビットコインETFとは?(仮想通貨ETFの違いや特徴) |
| 【初心者が始める】仮想通貨・暗号資産の積立投資 |
| 『超・初心者向け』仮想通貨・暗号資産 投資の方法 |
 日本人でビットコイン・仮想通貨を保有した投資家と運用リターンの仕組み
日本人でビットコイン・仮想通貨を保有した投資家と運用リターンの仕組み