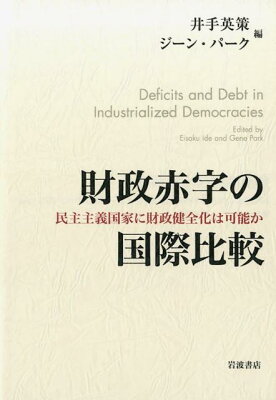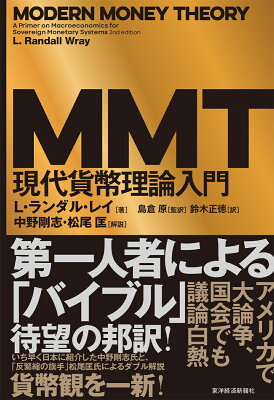なぜ日銀総裁は何がすごい?なぜ影響力を持つのか
日本の物価上昇と悪いインフレの代名詞である所得が上がらない問題
過度の円安。
異次元緩和という戦略をどうしてミスとして修正できないのか。
ふと小学生だったらいいそうなことを考えてみました。
政治家ならば、内閣解散、国民投票でリスタートという選択肢がある中、日銀総裁を引きずり落とすという記事を目にすることは滅多にありません。
実際、内閣や国会でも「日銀総裁を即時辞めてください」という発言があるにも関わらずそれ以上のことができないのはなぜか。
➡︎政府による金融・経済の介入にも負けない機関投資家の強さは何か
日銀総裁はクビにできない(ほぼ100%)
日銀総裁というのは、従来は政府が解任権を有していました。
しかし、現行法では解任権がなくなっています。
つまり、日銀総裁の任期である5年間は就任すれば、政府も国会も、国民も解任(クビ)にすることができない仕組みになっています。
日銀総裁はなぜ解任できないのか
簡単に言えば、政府や国会と表立って仲良くして都合の良いようにしてしまえば、日銀の総裁選挙で平等性や整合性、秩序が乱れるという理由です。
しかし、日銀自体はそもそも『政府の銀行』と呼ばれるほど関係性は密なので、完全独立組織になっているかというと違います。
*日本銀行の資本金は1億円のうち55%が政府から出資されています。
ちなみに政府と日銀は共同声明を発表する際、政府が前、日銀が後ろになっていることからパワーバランスはやはり政府が強いと言えます。
凡人・一般人にはわからない天才頭脳=日銀総裁の可能性
私たちが苦しむ異次元緩和の政策で、常軌を逸するほどの国債やETFの買い込みを行いました。
それにも関わらず、インフレは止まらず金利の高い国へ資金が流れるという悪循環に陥りました。=内外金利差の問題
その弊害は民間企業だけでなく、国民が各金融機関への預け入れを渋る結果となり、地銀などの経営は生き残ることに注力するしかない状態になりました。
そして、結果のシワ寄せは企業から国民へ行き、所得は増えずに物価は上がるという負の連鎖が起こりました。
私のような凡人が見ればこの金融政策は大失敗であり、企業であれば倒産、個人であれば自己破産寸前に陥られせた根源と考えてしまいます。
2%物価目標は不可能な壁を目指し実は『大成功』していた?
「2%物価目標」は実現しないとエコノミスト含め、多くの人間が確信していました。
理由としては、30年で1%すらインフレ率が上昇することがほぼない日本が2%の物価上昇など不可能なのはわかっている話のためです。
それでも2%は断固と譲らない姿勢を貫いた日銀総裁はある意味、本当のサイコパスなのか。天才なのか。
一般的に不可能なことをして日本は破産したか、というとそうではなくトヨタは最高純利益を叩き出し、輸出企業は爆発的な利益を何も変化させずとも叩き出せる仕組みは円安しかないのです。
仮に円高でこの爆発的な利益を出せるかというとそうではないのです。
日銀総裁の机上の空論はシナリオとして完璧だった可能性
そもそも輸入依存の日本でインバウンド需要で支えられた円高も、コロナ禍ではできず、金利を爆発的に上げてもそもそも銀行の普通預金に預け入れることしかしない国民性では外国の資本を増やすことにしかならないとも予想はできるのです。
コロナショックや地政学リスクを含め、私たちが知り得ないもっともっと広い視点で多くの水面化にあるのリスクを知る、日銀総裁としては大成功したと胸を撫で下ろしている可能性があるのです。
平均点すら取れない子供に100点がそもそも取れない試験で100点を目指させ、前回より良い点数を取らせた。
そう考えるとシナリオとして実は、クローザーとしての役割を果たしたと評価される一面もあるのです。
もちろん、その代償は日銀総裁として日々「無能だ、クビにしろ」という酷評に耐えることだったのかもしれません。
日銀総裁という影響力と権力に支払われるお金=年収・待遇
2020年度の日銀総裁の年収は3,529万円(内訳:役員棒給が2,412万円+役員手当が年間1,117万6,000円)
2023年の任期満了では退職金は過去の支払いから見ると5,000万円をゆうに超えるとされています。
念の為補足すると日銀の職員も総裁も公務員ではありません。
ですが、日本の金融で言えば総理大臣よりも給料が多いと、いろいろな面倒が出てきます。
そのため2020年の総理大臣の年収の約4049万円よりも低い算出になっていると言われています。
ちなみに国務大臣にあたる財務大臣の2020年の年収は約2953万円。
このことを踏まえると、総理大臣>日銀総裁>財務大臣となります。
さらに付け加えるとアメリカ大統領が日本の総理大臣よりも為替や物価に差があるにも関わらず額面上約200万円ほどしか変わらないことに驚きがあります。(2020年のアメリカ大統領の年収;4240万円)
![]()
出典元:日本経済新聞『首相は4049万円、閣僚の給料は安い?高い?』より
参考:日本銀行は、日本銀行法によりそのあり方が定められている認可法人であり、政府機関や株式会社ではありません。
日銀の権力・権限は凄まじい=為替加入の主役
為替介入はFXなどで投資する方々が聞くと、背筋が伸びる出来事ですが、為替介入はそもそも財務大臣が為替介入を必要と判断したら日銀が実行します。
為替介入の実務では財務大臣の代理人としての日本銀行が各国の中央銀行に為替介入を委託できる権限があります。
日銀内の全権限を有するのは当然ながら日銀総裁で、2022年度の為替介入に対する準備金は総額約180兆円相当(外貨売り、円買いの場合)
さらに言えば、仮に極度の円高の時には実質無制限に行うことができます。(外貨買い、円売り)
ここでMMT理論などが出てきますが、MMT理論の詳細は別のコンテンツをご参照ください。
参考:為替介入とは?
為替介入は強制的に市場の軌道修正をするかなり強引な方法です。
基本的に突発的偶発的天災等が行なった際に用いられる方法で、為替介入の仕組みは非常に簡単で、上げたい通貨、円安であれば『円』を大量に買い集めるということです。
円を大量に買えば必然的に円の価格は上がるので、この上がるトレンドラインに投資家は順張りしたいと考えるため、相乗的に通貨の価値を上げることができます。
過去の為替介入事例
2011年の東日本大震災時に1ドル75円台の「円高」時に、一日で8兆円分の米ドルを購入し円安へ軌道修正させました。
参考:MMTとは?
MMTは「Modern Monetary Theory」の略で『現代金融理論』とも呼ばれています。
現代貨幣理論の結論は日本であれば日本銀行などの中央銀行を保有する場合、財政破綻をすることはありえない。ということを論述しています。
参考図書
高額書物で翻訳は少し残念ですが、筆者は政治学が専門の学者が民主主義の構造が財政赤字にどう影響を与えているかを解説しています。
ちなみに、この本はフランス、ドイツ、イタリア、スウェーデン、アメリカ、韓国、日本の7カ国を対象にしていて、外国為替などの予備知識としても有益性があります。
財政赤字の国際比較 民主主義国家に財政健全化は可能か [ 井手英策 ]
この記事の筆者である私が『MMT』について深く知識を得た1冊
MMTによる解説が現在の経済の仕組みにおいて私たちがどれだけ、金融リテラシーがどれだけ脆弱かを知らしめるものとなります。
この本一冊で、『金融』の疑うべきポイントも気づけるはずです。【筆:熊崎】