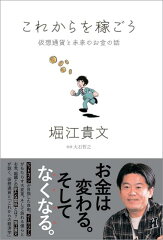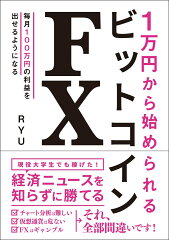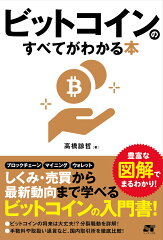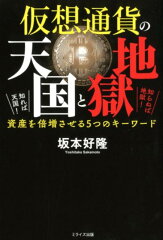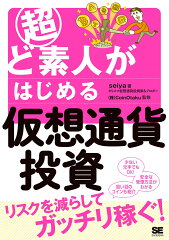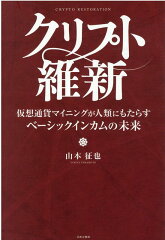なぜイーサリアムがあるのにイーサリアムクラシックに投資するメリットがあるのか。ETHとETCの差を解説
イーサリアムクラシック(ETC)とは
イーサリアムクラシック(ETC)とは分散型アプリケーション(DApps)やスマートコントラクトを構築するためのプラットフォームです。
最初からお分かりのとおり、イーサリアムと同じコンセプトで生まれた仮想通貨・暗号資産です。
この時点でなぜイーサリアムがあるのに、イーサリアムクラシック(ETC)が必要なのか。
投資をする側、利用する側は何を注目するべきか解説していきます。
参考:イーサリアム(ETH)という仮想通貨・アルトコインの優位性や特徴について
イーサリアムクラシック(ETC)はなぜ生まれたのか
The Dao事件がきっかけにイーサリアムクラシック(ETC)は生まれました。
THE DAO」事件とは
イーサリアム(ETH)が管理運営している『The DAO』のセキュリティにバグは発生し、約360万ETH(当時で50億円相当)の仮想通貨・暗号資産が不正に流出してしまう事件が起こりました(=「THE DAO」事件)
「THE DAO」事件の被害額は『イニシャル・コイン・オファリング(ICO)』で資金調達した総額約150億円の1/3以上と発表されました。
この「THE DAO」事件はイーサリアムだけでなく、仮想通貨・暗号資産・ブロックチェーン全体のセキュリティが疑われ、脆弱性が指摘されました。
【課題】NFTなどのスマートコントラクト分野でイーサリアムクラシック(ETC)は優位性を築けない
すでにNFTを活用するためにはイーサリアムが必要で、イーサリアムというのはアルトコインだ、という認知まで拡大した中で同じようなスマートコントラクトを利用した分野で独自性や優位性を築くことは難しいということが課題でした。
イーサリアムクラシック(ETC)の優位性はIoTプラットフォームとしての活用
イーサリアムクラシック(ETC)は、イーサリアムとの差別化という部分でIoTプラットフォームに着目しました。
IoT分野の特質上、非常に多くの情報処理が必要となります。
この処理速度は仮にクリアできても莫大なコストが掛かれば実用化は難しいと言えます。
イーサリアムはその点において弱点がありネットワーク使用状況に応じて手数料(ガス代)が変動します。
この変動する手数料(ガス代)が今のイーサリアムの収入源となっているため、これを定額化することは難しいと言えます。
ただでさえ、IoT分野は小さい情報を多く処理するためスケーラビリティ問題が発生しやすくなります。
この2つの点を解決することによってIoT分野はイーサリアムクラシック(ETC)が独占し優位性を高めようとしたのです。
イーサリアムとイーサリアムクラシックの差=コンセンサスアルゴリズム
イーサリアムクラシックは、PoW(Proof of Power)を採用しており、コンピューターの計算能力で取引が承認・マイニングされる仕組みとなっています。
このコンピューターのシステムによる取引承認やマイニングを行うことで非中央集権が揺るがないようにしています。
比べて、イーサリアムはまもなくPoS(Proof of Stake)に変更されます。
PoS(Proof of Stake)はPoW(Proof of Power)の代替システムとして発展しており、比較的新しいアルトコインには、PoSを採用しているケースが多いです。
PoS(Proof of Stake)の仕組みは、保有している枚数や所有期間により新たな取引が承認・マイニングされます。
そのため、イーサリアムを多く長く所有している人に権力が集中する可能性もあると言えるのです。
追記1:コンセンサスアルゴリズムとは
ブロックチェーンの運営・維持方法のルール・ガイドラインを意味し、承認権利や報酬などを決める際にも持ち入ります。
追記2:仮想通貨のコンセンサスアルゴリズムの種類
- PoS(Proof of Stake:プルーフ・オブ・ステーク)
- PoW(Proof of Work:プルーフ・オブ・ワーク)
- PoI(Proof of Importance:プルーフ・オブ・インポータンス)例:ネム(XEM)
- PoC(Proof of Consensus:プルーフ・オブ・コンセンサス)
イーサリアムとイーサリアムクラシックの差=発行上限枚数
イーサリアムクラシック(ETC)はコインの発行上限枚数が決まっており減少期を定めています。
イーサリアムクラシック(ETC)は発行上限枚数が約2億1,000万枚〜約2億3,000万枚と決まっており、500 万ブロックごとにマイニング報酬が 20 %ずつ減少します。
一方、イーサリアムには発行上限枚数がありません。
ビットコインやリップルなどの仮想通貨も同様に発行上限枚数が予め決まっています。
そのため、ゴールド(金)などと同様に価値が自然上昇する『希少性』を含んでいると考えられています。
経済紙などでは既に、『デジタルゴールド』とまでビットコインを呼ぶ声が出ています。
イーサリアムでも発行上限がありませんので、今後マイニングが続けられる限り新規のイーサリアムが安定して供給されることになります。
イーサリアムクラシック(ETC)の優位性=サイドチェーン 実装
イーサリアムクラシック(ETC)は、サイドチェーンの実装を目指しています。
サイドチェーンは、メインチェーンとは別のブロックチェーンを利用することで様々な機能の拡張が可能となり、スケーラビリティ対策としても有効です。
その結果としてスマートコントラクトの安定性も確保できるため、アルトコインとして実用性が高まります。
補足:スケーラビリティ問題とは
ブロックチェーン上の渋滞のことです。ブロックチェーンにユーザーが集中し過ぎて、取引処理の遅延や手数料の高騰が起きてしまう問題をスケーラビリティと言います。
イーサリアムとイーサリアムクラシックの差=51%攻撃とは…
イーサリアムクラシックが後発アルトコインであるために、差別化や優位性を作り出すチャンスは今後もありますが唯一投資での危惧するポイントも説明していきます。
『51%攻撃』というリスクを抱えている点です。
なぜイーサリアムクラシックだけが51%攻撃のリスク対象になるかというと前述したコンセンサスアルゴリズム
PoW(Proof of Work)に原因があります。
PoWの承認の仕組みは簡単に言えば『多数決』です。
PoWは1つの取引承認に対して複数のコンピューターや端末で51%以上の承認で可決されて実行されます。
つまり、100台仮にパソコンなども端末があり、51台が虚偽の取引承認を行うとブロックチェーン上では正しい答えになってしまうのです。
過去にイーサリアムクラシック3度の51%攻撃を受けており、投資や運用先として選定する中の不安要因であり危惧するポイントだと言えます。
なぜイーサリアムがあるのにイーサリアムクラシックに投資するメリットがあるのか。(まとめ)
- イーサリアムクラシック(ETC)はIoTプラットフォームの分野で優位性を期待できる
- イーサリアムクラシック(ETC)は、PoWによって非中央集権が揺るがないようにしています。
- ビットコインやリップルなどの仮想通貨も同様に発行上限枚数が予め決まっている。
- 中長期的に『希少性』を期待できるアルトコイン
- イーサリアムクラシック(ETC)サイドチェーンの実装
- スケーラビリティ対策
- 51%攻撃への危惧
この上記7項目でIoTプラットフォームの分野で優位性を期待できる点と、発行上限枚数が決まっている点を考えると安心材料が揃っているようにも見えます。
それに加え「THE DAO」事件の経験を活かし一部の人たちの意向や利害によって運営方針が決められることは今後ないという点も好感を感じる部分です。
しかし、そんな民主主義のような仕組みよりも危惧・懸念されるセキュリティ問題、そして最大の期待値であるIoTプラットフォームの分野の功績が生まれるかどうかという点で、開発力やコミットの実現性を判断する必要があると言えます。