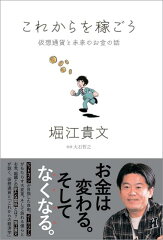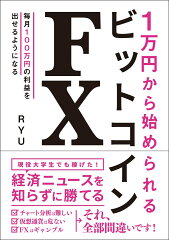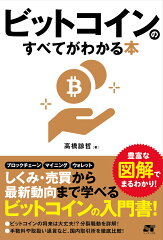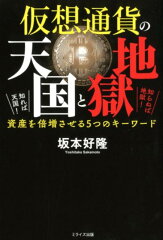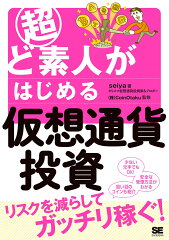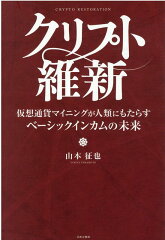- 1. ポルカドット(polkadot)が『稼げる』『期待できる』仮想通貨として注目される優位性は何か
- 2. ポルカドット(Polkadot)の『Web3.0』とは?
- 3. ポルカドット(polkadot)が企業への依存を無くす『Web3.0』を作る
- 4. ポルカドット(polkadot)の期待値=インターオペラビリティを実現できる
- 5. ポルカドット(polkadot)の優位性=スケーラビリティ問題を解決している
- 6. ポルカドット(polkadot)の優位性=ハードフォークを行わずにアップグレードが可能
- 7. ポルカドット(polkadot)の優位性=セキュリティ性能の高さ
- 8. ポルカドット(polkadot)の優位性=オープンガバナンス体制
- 9. 【稼ぐポイント】ポルカドット(polkadot)の優位性=ステーキングサービス
- 10. NFTに関連する仮想通貨・暗号通貨『ポルカドット(Polkadot)』=エンジン(Enjin)との関係
- 11. 補足:Enjinの優位性=『Enjin Platform』
- 12. ポルカドット(polkadot)が『稼げる』『期待できる』仮想通貨として注目される優位性をまとめる
- 13. 『次のイーサリアム』=ポルカドットの特徴【優位性のまとめ】
ポルカドット(polkadot)が『稼げる』『期待できる』仮想通貨として注目される優位性は何か
ポルカドット(polkadot)とは
ポルカドット(polkadot)は、元イーサリアムの共同創設者で元CTOのギャビン・ウッド氏が設計をしました。
既にイーサリアムのデータやノウハウを持った上で設計された仮想通貨が生まれたことになります。
後発だからこそ、イーサリアムができないことや利便性が低い部分を払拭していくスタイルが『次のイーサリアム』というように評価されたようです。
ポルカドット(polkadot)のビジョンは『Web3.0という世界の実現を目指すプロジェクト、およびそのためのブロックチェーンを生み出すこと』としています。
ポルカドット(Polkadot)の『Web3.0』とは?
ポルカドット(Polkadot)のWeb3.0とはどんな世界をイメージすればいいのかというと、ブロックチェーンによって分散型(非中央集権型)の新しいWeb環境です。
ちなみに現在はWeb2.0世代でSNSの普及により閲覧だけでなく発信ができるWeb環境のことを言います。
それより前にはWeb1.0があり、ホームページの情報を閲覧のみする一方通行のWeb環境を言います。
現在のWebやインターネットの環境はGAFAや日本で言えば楽天、ZOZOTOWNなどの企業がサービスや商品を提供しています。
それ以外の存在は基本的にサービスを利用する側であり、サービスを提供する側にはなりにくい環境です。
何が言いたいかというと、企業へ依存しなければ生活が不自由になっている時代(=Web2.0)なのです。
ポルカドット(polkadot)が企業への依存を無くす『Web3.0』を作る
例えば不用品を売買する際、フリーマーケットを使えば直接やり取りができるため手数料はかかりません。
しかしフリマアプリを使うには会員登録(個人情報の提供)や手数料がかかり、このフリマアプリに依存しなければ売買ができないという中央集権の拘束力が発生します。
仮にも利用しているフリマアプリがなくなった場合、出金していない売上金はどこにいくか考えると不安になるはずです。
このような企業を信用せざるを得ない環境になっているのをポルカドット(polkadot)は、買い手と売り手を一対一でつなげ、中央管理者が存在しない仕組みにしていこうと考えているのです。
この中央集権制や中央管理者である企業は顧客の情報を一か所に集める必要がなく、流出する心配もないのです。
これは企業にとってもリスクヘッジになりますし、利用者も個人情報を企業への信頼だけで開示する必要がなくなるのです。
この中央管理者を不要にするポルカドット(polkadot)の仕組みは「分散化」と位置づけられ、分散化されたインターネットの空間=「web3.0」としています。
ポルカドット(polkadot)の期待値=インターオペラビリティを実現できる
異なるブロックチェーン間に相互運用性はない
この説明の前提認識として、仮想通貨や暗号資産には互換性が基本的にないということを頭に読み進めてください。
インターオペラビリティとは、和訳すれば相互運用性です。
簡単に言えば、ブロックチェーンが異なれば互換性がないため繋ぐことができませんでした。
イメージはソニー製テレビのリモコンでパナソニックのテレビを操作できないのと同じ意味です。
逆に、銀行などは三井住友銀行に預けてもその他の金融機関へ送金ができるのは互換性があるという解釈になります。
この相互運用性があれば互換性のないブロックチェーンも、ポルカドット(polkadot)が繋ぎ合わせる役目を持つためわざわざ取引所などで換金する必要がなくなるのです。
つまりブロックチェーンの普及にブロックチェーン自体に互換性がないことが障害にならぬように相互運用性・相互性を上げるための仕組みを研究したりプログラムを開発することをインターオペラビリティと言います。
脱 中央集権制=完全な分散型のWebの世界⇨Web3.0にはポルカドット(polkadot)が必要
ポルカドット(polkadot)の優位性=スケーラビリティ問題を解決している
スケーラビリティ問題とは、ブロックチェーン上の渋滞のことです。
ブロックチェーンにユーザーが集中し過ぎて、取引処理の遅延や手数料の高騰が起きてしまう問題をスケーラビリティと言います。
ビットコインでもスケーラビリティ問題は課題だとされていました。
そのためスケーラビリティ対策でサイドチェーンをビットコインが駆使するようにポルカドット(polkadot)は、「Parachain(パラチェーン)」と呼ばれる並列化されたブロックチェーンを実装しました。
この並列化されたブロックチェーンによりトランザクションの効率的になり、取引処理の遅延や手数料の高騰が起きてしまう問題をスケーラビリティの解決策として打ち出しています。
ポルカドット(polkadot)の優位性=ハードフォークを行わずにアップグレードが可能
ビットコインやイーサリアムなどの仮想通貨は、機能改善などのアップグレードには、ハードフォークという方法を用います。
【補足】ハードフォークの意味と種類
ハードフォークの逆の意味で『フォーク』という言葉もあり、これはアップグレードをしなかった仮想通貨です。そしてその間には『ソフトフォーク』があります。
つまり、バージョンが上がったもの同士は互換性がありますが、バージョンを上げていない『フォーク』の仮想通貨とは互換性がなくなったという考えでいましょう。
その間に位置づいているソフトフォークはクルマで言えば『マイナーチェンジ』に似ており、互換性を維持したままのアップグレードを行ったことを意味します。
ポルカドット(polkadot)の開発を手掛けた元イーサリアムの共同創設者で元CTOのギャビン・ウッド氏は、ハードフォークによる非効率性を問題視していたのでしょう。
そのため、ポルカドット(polkadot)というお店がクローズ状態の時間を作らないようにハードフォークなしでのアップデートを可能にしました。
ポルカドット(polkadot)の優位性=セキュリティ性能の高さ
ポルカドット(polkadot)は、『Pooled Security』と呼ばれるセキュリティプログラムがネットワーク上にプールされています。
その、『Pooled Security』は各ブロックチェーンで活用できるようになっているため、従来のブロックチェーンのセキュリティより効率的で性能が高いと言えます。
ちなみに、従来型のブロックチェーンのセキュリティは一つ一つのブロックチェーンごとにリソースを割く必要があり、メインチェーンであれば問題なくとも小さいブロックチェーンではリソース枠が確保できず脆弱性がありました。
ポルカドット(polkadot)の優位性=オープンガバナンス体制
オープンガバナンス体制とは、ユーザーが協働してネットワークの発展に取り組む仕組みのことです。
このユーザー定義が各仮想通貨やブロックチェーンによって異なります。
ポルカドット(polkadot)のユーザーはポルカドット(polkadot)保有者のみとなっています。
ポルカドット(polkadot)保有者のみがガバナンス権を付与され、具体的にネットワーク内の手数料の決定やブロックチェーンの追加・削除、プロトコルのアップデートなどを取り決める一員になることができます。
【稼ぐポイント】ポルカドット(polkadot)の優位性=ステーキングサービス
ステーキングとは
ステーキングサービスとは、対象の仮想通貨を保有することでブロックチェーンに参加し、報酬を受け取る仕組みのことです。
簡単に言えば、をポルカドット(polkadot)を保有しているだけで利子・配当益(インカムゲイン)を受け取るということです。
インカムゲイン狙いで長期保有するという運用方法を選択することが視野に入れられるため、ポートフォリオを組む際に候補に挙げることができる仮想通貨だといえます。
ポルカドット(polkadot)はWeb3.0、ブロックチェーンの発展に貢献しているという評価が目立ち、仮想通貨市場2位の時価総額を持つイーサリアムが影になるほどの影響力を持とうとしています。
『次のイーサリアム』=ポルカドットの特徴【優位性のまとめ】
- ポルカドット(polkadot)は、元イーサリアムの共同創設者で元CTOのギャビン・ウッド氏が設計している
- 企業へ依存しなければ生活が不自由になっている時代(=Web2.0)の脱却=Web3.0世代をリードしている
- インターオペラビリティを実現できる
- スケーラビリティ問題を解決できる
- ハードフォーク不要のアップデートが可能であること
- セキュリティ性能が高い
- オープンガバナンス体制を取っている
- ステーキングサービスの対象通貨であること