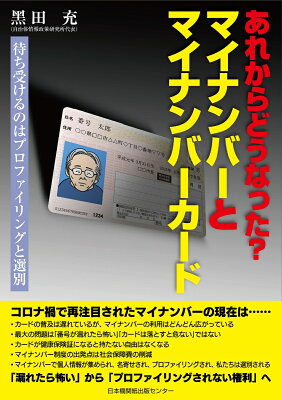知っているようで知らない・わからないマイナポイントとは?
マイナポイント事業とマイナポイントとは?
マイナポイント事業は、消費の活性化やマイナンバーカードの普及促進、ここ数年で盛り上がりを見せているキャッシュレス決済の基盤構築を目的とした国の施策です。
マイナポイントは消費の活性化やマイナンバーカードの普及促進が目的
キャッシュレス決済サービスの利用を通じて獲得できるものです。
このマイナポイントは国から消費者へ直接付与ではなく、キャッシュレス決済事業者から消費者へ、
『利用しないと使えない』という消費を促す仕組みになっています。
補足【マイナポイント申込期間】
終了 第1弾:2020年7月1日(水)~2021年12月31日(金)
※2021年4月30日(金)までにマイナンバーカードを申請した方が対象になります。
※2021年12月31日までに上限5,000ポイントまで付与を受けていない方は、2022年1月1日以降も2023年2月28日までの期間、上限5,000ポイントまで付与されます。
第2弾:2022年1月1日(土)~2023年2月28日(火)
※マイナンバーカードを新規に取得した方(マイナンバーカードを既に取得した方のうち、現行マイナポイントの未申込者を含みます)が対象になります。
マイナポイントが付与される仕組み
マイナポイントの受け取る・獲得するには『マイナンバーカード』『マイキーID』が必要で、マイキーIDで設定しない限りマイナポイントは利用もできません。
このマイキーIDの発行はスマホが最も簡単ですが、スマホがない方は市区町村窓口・郵便局・コンビニ・携帯ショップなどでマイナポイント用の支援端末の貸し出しがあります。
マイナンバーカード
マイナンバーカードとは、国内での行政手続きにおいて個人を識別するために国民1人1人に割り当てられた12桁の個人番号(マイナンバー)が記載されたカードの通称で、「個人番号カード」とも呼ばれます。
*通知カードとマイナンバーカードは異なります
マイキーID
マイキーIDとは、ウェブ上のマイキープラットフォームで設定されるIDです。本人認証に使用されます。
この記事だけで『マイキーID』の発行をしてみる
できれば理由があるため、この記事を最後まで読んでから発行してみてください
まずは「マイナポイント」アプリのダウンロード
マイナポイントの予約にはスマートフォンから「マイナポイント」アプリのダウンロードが必要です。
*パソコンで発行すると大きな文字で見やすいですが、ICカードリーダ必要であり、スマホの方がダウンロードが簡単で時短になります。
- iPhoneの場合
「マイナポイント」アプリをダウンロード - Androidの場合
「マイナポイント」アプリをダウンロード - パソコンの場合
マイキープラットフォームを開く
マイナンバーカードの読み取り
「マイナポイント」アプリを起動し、アプリの指示に従って「マイキーIDの発行」をタップするとマイナンバーカードを読み取る画面になります。
その後、すぐにマイキーIDが発行されます。
マイナンバーカードの読み取り時に暗証番号が必要です。(マイナンバーカード受け取り時に設定した4桁の数字・失念した場合はこちらから再設定も可能です)
マイナポイントで使える決済サービス
ほとんどの決済サービスでマイナポイントの利用ができます。
QRコード支払い
LINE Pay カード(JCBプリペイド)QUICPay+、など
オンライン支払い
Visa LINE Payプリペイドカード(海外加盟店での利用を含む)Visa LINE PayプリペイドカードをApple PayやGoogle Payに設定した支払いが対象です。
上記の支払い方法であれば、LINE Pay残高からのお支払い、チャージ&ペイ(Visa LINE Payクレジットカード登録)での支払いのどちらも対象です。
マイナポイントをクレジットカード・デビットカードで使うこともできる
マイナポイント事業に採用されているサービスとしては、三井住友カードやJCB、楽天カードやイオンカード、地方銀行の提供クレカでも利用は可能です。
家族名義の決済サービスでは申し込み不可
マイナポイントが申し込めるのは、本人名義のキャッシュレス決済サービスのみです。
家族名義や他人のキャッシュ決済サービスでは申し込めません。
未成年の子供は、親名義のキャッシュレス決済サービスで申し込むことが可能です。
楽天カードなどを利用している方は家族カードを利用している場合も多いと思います。
楽天カードを含めマイナポイントに申し込むことはほとんどが家族カードでは申し込みができません。
(au PAYカード・イオンカードは執筆時は可能)
家族間でポイントの合算・譲渡はできない
子供にお小遣いとしてあげたい・祖父母がくれると言っている場合は?
いかなる場合でも家族分のマイナポイントを、ひとつのキャッシュレス決済サービスにまとめて紐づけることはできません。
ただし、子供が15歳未満の場合は親または法定相続人がマイナンバーカードを発行申請し、カードを受け取る際は親、または法定相続人が同行する必要があります。
子供が15歳以上の場合は子供が自分で申請手続を行います。
その際カードの受け取りは子供本人のみでOKです。
生後すぐの赤ちゃんは出生届を提出して「マイナンバー通知書」を発行してもらっておくと手続きがスムーズです。
知っているようで知らない・わからないマイナポイントの秘密
このマイナンバーカードやマイナポイントとは毎年3000億円ほどの経済効果・利益が発生すると政府は発表しています。
しかし、政府がマイナポイントを発行したり、還元してもマイナンバーカードの維持などの費用を考慮するとエビデンスは非常に少ないということです。
むしろ、日本でマイナポイントを利用できるようにインフラを整備するため、全国の中小企業含めすべての事業者を含めると総額3兆円のコストがかかります。(シンクタンクの試算)
マイナンバーカード・マイナポイントは誰が得する仕組みなのか
通知カードからマイナンバーカードの発行に躊躇する人々
マイナンバーカードを勤め先や転職先などに提出を求められたという経験があると思います。
そのため、結果としてマイナポイントを受け取ることになったという方もいるはずです。
しかし、
事業主や経営者からすれば、法律上集めるようにと指示はされますが、従業員側に義務がありません。
職場・企業が従業員のマイナンバーの管理する
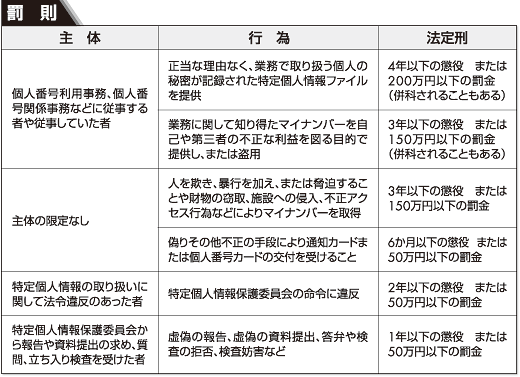
出典元:全商連「知っていますかマイナンバー」より
事業主・経営者はマイナンバーに対してメリットはないですが、マイナンバーの管理には非常に思い重い罰則があります。
万が一、仮に従業員のマイナンバーが流失した場合、事業や企業運営は経営の危険を伴う可能性があります。
さらに、事業主はマイナンバーに対応するための費用は対応するパソコンソフトの導入などで従業員数「5人以下」「6~20人」では40万円台、「21~50人」66万円、「51~100人」99万円と推計されています(帝国データバンク調査)
通知カードからマイナンバーカードの発行に躊躇する理由
そもそも従業員のマイナンバーカードを集める事業者目線で言うと、給料所得などの管理を政府にされる=中央管理する仕組みとしか考えることができません。
それを証拠に、証券会社の口座開設などでもマイナンバーカードの番号が必須になっています。
つまり、今でも調べることは比較的容易ですが、借入や土地・有価証券等の本当の個人の資産状況を把握するためのものという位置付けになるのです。
マイナンバーカードの普及率
「マイナポイント」事業はなぜ始まったのか、というと普及率が悪かったという背景があります。
2021年度のデータでは普及率は3日時点で40.0%と総務省が発表しました。(交付枚数は約5069万枚)
そして執筆時現在は43.3%。
政府は2022年末までに全日本国民への普及(普及率100%)を目指しているが到底追いつかないことになります。
すなわち、それだけマイナンバーカードを発行することに躊躇する方々が多いということになります。

マイナポイントでマイナンバーカードの普及率が上がらない場合
マイナポイントはマイナンバーカードの普及率を飛躍させる起爆剤として用いられています。
しかし、それでもマイナンバーカードの普及率が上がらない場合どうなるのでしょうか?
マイナンバーカードはあらゆるインフラと紐付けができるようになっています。、元々システムが構築されており、保険証や運転免許証・銀行口座などと紐付けは容易にできます。
そのため、マイナンバーカードがなければ日本では生活しにくい状況に追い込む可能性はあります。
『ただより高いものはない』
マイナポで個人情報がどれだけ見られるか(法律面)
マイナポイントのきっかけにマイナンバーカードを作った方は、政府を信用するかどうかよりもポイントに有益性を感じた方が多いはずです。
政府が作った仕組みやシステムだからこそ個人情報は大丈夫だと安心する方もいると思いますが、現時点で、
「刑事事件の捜査、租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査または会計検査院の検査」(マイナンバー法19条12)に該当するときは
(1)個人番号の利用範囲の限定(9条)
(2)特定個人情報提供の制限(19条)
(3)特定個人情報の収集・保管の制限(20条)
などの規制は対象外になっています。
=警察や税務署はなんの規制もなく特定の個人情報を閲覧できる
参考図書
この記事を読み、「よし、マイナポ貰おう!」と思った方は逆にあまりおすすめしない本です。
しかし、長期的な歴史の流れまでもマイナンバー制度をベースに比較対象しているため、マイナンバーの本質や狙いというのは金融リテラシーとして知っておくべきでしょう。